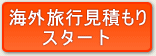Jump to navigation
2005-09-29
海外旅行保険はほんとに必要?(最終回)
今まで下がっても7度少しあった熱が、パリに来てからずっと平熱に下がっていた。 太ももの紫斑も少しずつ薄くなってきている。美味しい食事にありつけたからだろうか?
その日の午後、日本人とフランス人ドクターが入ってきて「骨髄検査の結果がでたよ」とまた白い紙を持ってきた。
「検査の結果、あなたの骨髄には異常はありません。」
ドクターはそういってニコッと笑った。
「異常なし? じゃあなんで血小板と白血球が減ってるの?」
「あなたトルコで点滴受けてたでしょ、あの点滴の中にダラシンという抗生物質が入ってて、それがあたなの身体の中でアレルギー反応を起こして血小板と白血球を壊していってたの。」
ちょっとややこしい話で、ボクはすぐには理解できなかった。
「簡単に言うと、熱を下げるために受けてた点滴があなたの血小板と白血球を潰していってたわけ。日本では点滴する前にアレルギーチェックするけど、外国ではあまりしないからね。」
以前、日本で点滴したことがあるが、確かに点滴を打つ前に皮膚にフプチっと針をさしていた。
「じゃあ、あのままトルコに入院していたら死んでた?」
「そりゃあいくら輸血しても壊していってるんじゃ何にもならないからね。ここに来てなければ2,3日ってところだったんじゃない。急性紫斑血小板減少症っていう病気よ。」
「くそ!あの野郎!」
ボクはあの浅黒いトルコのドクターを思い浮かべていた。
「じゃあ骨髄に異常がないってことは、このまましばらくすると血小板も白血球も増えてくるんですよね?」
「そうね、もうだいぶ増えてきてますよ。脚の紫斑が消えてきてるでしょ。」
「じゃあこのまま旅を続けられますね?」
「それはダメですよ、お母さんと一緒に日本に帰りなさい。」
ドクターは手を横に振って「だめだめ」と言っていた。母親も「そうそう」とうなずいている。
その日の夜、日本にいる父親から電話がかかってきた。
骨髄に異常がなかったのでこのまま旅を続けたいというと
「おまえ、もうそこまでやったら日本帰ってこないとダメだ!」
とかなり激怒していた。
でもボクはここで旅をやめるわけにはいかない。その日の夜にドクターにお願いした。
「ドクター、ボクの骨髄に異常ないんならあとは大丈夫だよね。旅を続けられると母親に言ってくれ。」
その後、何度となくドクターに頼み込み、二つの条件をのむということで旅を続けてもいいとOKをもらった。
一つ目の条件は、一ヵ月後にどこからでもいいから血液検査をしてその結果をFAXで送ること。二つ目は今度7度5分以上の熱がでたら必ず病院へ行くこと。
「パスポートの後ろにでもダラシン・ショックって書いときなさい。事故とかの時にわからずにまた点滴されるかもしれませんからね。」
ボクは「ありがとう」と彼女に礼を言って、母親が持ってきたインスタントの日本食をプレゼントした。
アメリカン・ホスピタルを退院したボクは母親が泊まっているホテルに移った。部屋には保険会社の人が持ってきたという大きなフルーツがおいてある。母親にはせっかくパリまで来たのだから、パリ見物でもして帰ったらと言ったが、とてもそんな気持ちにはなれないと早々に帰国した。
結局今回のことは熱を下げるために打った点滴が仇となったかたちだった。あのままトルコの病院に入院していたらほんとに死んでいた。
後で聞いた話だが、パリの病院が1泊10万円で一週間入院、それに骨髄検査。トルコの病院はいくらかわからないけど一週間入院と輸血。それからトルコからパリへのフライト代がなんと300万円! それプラス母親のパリ往復チケットが50万円とホテル代が4泊分。ボクは600万円までOKの保険に入っていたのだか、大方使ってしまったんじゃないだろうか?
もし保険に入ってなかったら300万なんてフライト代出せるわけもなく、きっとトルコで死んでたに違いない。やっぱり海外旅行保険には入っておかないとダメだ。入っててよかったとつくづく思った。
ちなみにもしトルコから日本に飛行機飛ばしてたら2000万だったそうだ。恐ろしい!
その後ボクはパリからヨーロッパ、北米、中南米、アジアとまわり、旅はまだまだ続いた。結局帰国したのはパリでの入院から2年半後だった。
その日の午後、日本人とフランス人ドクターが入ってきて「骨髄検査の結果がでたよ」とまた白い紙を持ってきた。
「検査の結果、あなたの骨髄には異常はありません。」
ドクターはそういってニコッと笑った。
「異常なし? じゃあなんで血小板と白血球が減ってるの?」
「あなたトルコで点滴受けてたでしょ、あの点滴の中にダラシンという抗生物質が入ってて、それがあたなの身体の中でアレルギー反応を起こして血小板と白血球を壊していってたの。」
ちょっとややこしい話で、ボクはすぐには理解できなかった。
「簡単に言うと、熱を下げるために受けてた点滴があなたの血小板と白血球を潰していってたわけ。日本では点滴する前にアレルギーチェックするけど、外国ではあまりしないからね。」
以前、日本で点滴したことがあるが、確かに点滴を打つ前に皮膚にフプチっと針をさしていた。
「じゃあ、あのままトルコに入院していたら死んでた?」
「そりゃあいくら輸血しても壊していってるんじゃ何にもならないからね。ここに来てなければ2,3日ってところだったんじゃない。急性紫斑血小板減少症っていう病気よ。」
「くそ!あの野郎!」
ボクはあの浅黒いトルコのドクターを思い浮かべていた。
「じゃあ骨髄に異常がないってことは、このまましばらくすると血小板も白血球も増えてくるんですよね?」
「そうね、もうだいぶ増えてきてますよ。脚の紫斑が消えてきてるでしょ。」
「じゃあこのまま旅を続けられますね?」
「それはダメですよ、お母さんと一緒に日本に帰りなさい。」
ドクターは手を横に振って「だめだめ」と言っていた。母親も「そうそう」とうなずいている。
その日の夜、日本にいる父親から電話がかかってきた。
骨髄に異常がなかったのでこのまま旅を続けたいというと
「おまえ、もうそこまでやったら日本帰ってこないとダメだ!」
とかなり激怒していた。
でもボクはここで旅をやめるわけにはいかない。その日の夜にドクターにお願いした。
「ドクター、ボクの骨髄に異常ないんならあとは大丈夫だよね。旅を続けられると母親に言ってくれ。」
その後、何度となくドクターに頼み込み、二つの条件をのむということで旅を続けてもいいとOKをもらった。
一つ目の条件は、一ヵ月後にどこからでもいいから血液検査をしてその結果をFAXで送ること。二つ目は今度7度5分以上の熱がでたら必ず病院へ行くこと。
「パスポートの後ろにでもダラシン・ショックって書いときなさい。事故とかの時にわからずにまた点滴されるかもしれませんからね。」
ボクは「ありがとう」と彼女に礼を言って、母親が持ってきたインスタントの日本食をプレゼントした。
アメリカン・ホスピタルを退院したボクは母親が泊まっているホテルに移った。部屋には保険会社の人が持ってきたという大きなフルーツがおいてある。母親にはせっかくパリまで来たのだから、パリ見物でもして帰ったらと言ったが、とてもそんな気持ちにはなれないと早々に帰国した。
結局今回のことは熱を下げるために打った点滴が仇となったかたちだった。あのままトルコの病院に入院していたらほんとに死んでいた。
後で聞いた話だが、パリの病院が1泊10万円で一週間入院、それに骨髄検査。トルコの病院はいくらかわからないけど一週間入院と輸血。それからトルコからパリへのフライト代がなんと300万円! それプラス母親のパリ往復チケットが50万円とホテル代が4泊分。ボクは600万円までOKの保険に入っていたのだか、大方使ってしまったんじゃないだろうか?
もし保険に入ってなかったら300万なんてフライト代出せるわけもなく、きっとトルコで死んでたに違いない。やっぱり海外旅行保険には入っておかないとダメだ。入っててよかったとつくづく思った。
ちなみにもしトルコから日本に飛行機飛ばしてたら2000万だったそうだ。恐ろしい!
その後ボクはパリからヨーロッパ、北米、中南米、アジアとまわり、旅はまだまだ続いた。結局帰国したのはパリでの入院から2年半後だった。
2005-09-25
海外旅行保険はほんとに必要?(part5)
ボクを乗せた車は空港へ向かわず広い空き地のようなところで止まった。金網のフェンスが続きゲートには銃を持った兵士が立っている。どうやらここは軍用飛行場らしい。
「いくら病院から近いといっても軍用飛行場に飛んで来るとは。。。」
ゲートをくぐると小さな自家用ジェットの前に二人の男が立っていた。
「Are you SHUSA?」
30代半ばくらいだろうか、その男はボクの名前を尋ね、自分はパリから来たドクターだと言った。もうひとりの男は看護士らしい。
ジェットに乗り込むとボクはジーンズをめくって自分の脚を見せた。実は昨日あたりから太股など軟らかいところに紫色の斑点が無数にでていた。皮下出血している証拠だった。
「ドクター見てくれ、脚全部に紫斑がでてる。パリまでもつかな、死んじゃうんじゃないかな。」
「no problem」
ドクターはそういってボクを簡易ベッドのような上に寝かせ、腰と胸のあたりにシートベルトで固定した。
カイセリを主発した飛行機は一度イスタンブールに降りる。ボクは寝かされたままだが、ここで係官が乗り込んできて出国審査をする。ボクもパスポートにスタンプを押してもらった。まさかこんなフライトでも出国審査をするとは思わなかった。
それからすぐ飛び立つとドクターと看護士は機内食を取り出して食べだした。
機内はパイロット二人を含めて5人。まるで車の後部座席に座っているようにコックピットは丸見えだ。こんな経験はもちろん初めてだったが、離着陸以外パイロットは何もしていない、気楽な感じだった。
「君も食べる?」
ドクターはボクがじろじろ見ているので欲しいのかと思って訊いてきた。
「あるんだったら食べるよ、病院ではまともなもの食べてなかったから。」
その機内食にはビックリした。スモークサーモンや何やらで凄いメニュー、さすがフランスから来ただけある。ビスケットしか食べてなかったボクは久しぶりに食事らしい食事に感激した。
 パリに着いたのは夜、ボクは救急車で病院に運ばれた。「American hospital」と言って外国人専用らしく、トルコの大学病院とは比べ物にならない。
パリに着いたのは夜、ボクは救急車で病院に運ばれた。「American hospital」と言って外国人専用らしく、トルコの大学病院とは比べ物にならない。
病室に運ばれるとドクターが二人入ってきた。女性の方は日本人らしく日本語を話した。
「見てください、もうこんなに紫斑が。。。。。」
ボクは脚全体に広がっている紫斑を彼女にみせた。
彼女はもう一人のドクターとなにやらフランス語で話すと「大丈夫ですよ」といって笑ってみせる。その「大丈夫」も何やら怪しい感じがした。
「とにかく血液検査をします。明日までゆっくり休んでください。」
うなずくしかできないボクは久しぶりにふかふかのベッドで眠った。
翌日は朝から大忙しだった。保険会社のセンター、大使館、日本にいる親とひっきりなしに電話がかかってくる。
血液検査の結果はやはり血小板が異常に下がっているままだった。
「すぐに骨髄の検査をします。」
英語でボクに話すドクターを彼女が通訳してくれた。ボクは「とにかくなんでもやってくれ」みたいな返事をしたのを憶えている。
とにかくここの設備は凄かった。ベッドは電動で起きあがるし、もちろんエアコン、トイレ、バス、衛星放送まで付いている。
食事がまた凄い。昼食が終わると看護士が1枚の紙を持ってくる。そこには夕食のメニューが書かれていて、メインは魚かビーフ、デザートはアイスかケーキなどすべて自分で選択できるのだ。すべてチェックを入れると夕食にはそれが出てくる。
「さすがアメリカン・ホスピタル、水までエビアンだ。」
それもそのはず、後で聞いた話だがこの病室は1泊10万円だったそうだ。
 ここに入院して3日目くらいだったろうか、突然病室に母親が現れた。いても立ってもいられなく、今日日本から来たらしい。
ここに入院して3日目くらいだったろうか、突然病室に母親が現れた。いても立ってもいられなく、今日日本から来たらしい。
半年ぶりに見る母親は泣きそうな顔をしていたが、結構元気そうなボクをみて安心していた。日本ではもう死にかけと聞いていたので、もっとひどい状態だと思っていたらしい。
ボクは母親が来たのにも驚いたが、その荷物の多さにもっと驚いた。彼女はカバン一杯に即席麺、お茶づけ海苔、レトルトカレーにご飯などなどパリでコンビニでもするつもりなのかと思うほど買い込んでいた。
「だってトルコの大使館の人が、息子さん食欲なくて困っているみたいなので、行くならたくさん日本食持っていってあげてくださいっていってたから。。。」
翌日、とうとう骨髄検査の結果が出た。。。。。。。。。。To be continued
「いくら病院から近いといっても軍用飛行場に飛んで来るとは。。。」
ゲートをくぐると小さな自家用ジェットの前に二人の男が立っていた。
「Are you SHUSA?」
30代半ばくらいだろうか、その男はボクの名前を尋ね、自分はパリから来たドクターだと言った。もうひとりの男は看護士らしい。
ジェットに乗り込むとボクはジーンズをめくって自分の脚を見せた。実は昨日あたりから太股など軟らかいところに紫色の斑点が無数にでていた。皮下出血している証拠だった。
「ドクター見てくれ、脚全部に紫斑がでてる。パリまでもつかな、死んじゃうんじゃないかな。」
「no problem」
ドクターはそういってボクを簡易ベッドのような上に寝かせ、腰と胸のあたりにシートベルトで固定した。
カイセリを主発した飛行機は一度イスタンブールに降りる。ボクは寝かされたままだが、ここで係官が乗り込んできて出国審査をする。ボクもパスポートにスタンプを押してもらった。まさかこんなフライトでも出国審査をするとは思わなかった。
それからすぐ飛び立つとドクターと看護士は機内食を取り出して食べだした。
機内はパイロット二人を含めて5人。まるで車の後部座席に座っているようにコックピットは丸見えだ。こんな経験はもちろん初めてだったが、離着陸以外パイロットは何もしていない、気楽な感じだった。
「君も食べる?」
ドクターはボクがじろじろ見ているので欲しいのかと思って訊いてきた。
「あるんだったら食べるよ、病院ではまともなもの食べてなかったから。」
その機内食にはビックリした。スモークサーモンや何やらで凄いメニュー、さすがフランスから来ただけある。ビスケットしか食べてなかったボクは久しぶりに食事らしい食事に感激した。

病室に運ばれるとドクターが二人入ってきた。女性の方は日本人らしく日本語を話した。
「見てください、もうこんなに紫斑が。。。。。」
ボクは脚全体に広がっている紫斑を彼女にみせた。
彼女はもう一人のドクターとなにやらフランス語で話すと「大丈夫ですよ」といって笑ってみせる。その「大丈夫」も何やら怪しい感じがした。
「とにかく血液検査をします。明日までゆっくり休んでください。」
うなずくしかできないボクは久しぶりにふかふかのベッドで眠った。
翌日は朝から大忙しだった。保険会社のセンター、大使館、日本にいる親とひっきりなしに電話がかかってくる。
血液検査の結果はやはり血小板が異常に下がっているままだった。
「すぐに骨髄の検査をします。」
英語でボクに話すドクターを彼女が通訳してくれた。ボクは「とにかくなんでもやってくれ」みたいな返事をしたのを憶えている。
とにかくここの設備は凄かった。ベッドは電動で起きあがるし、もちろんエアコン、トイレ、バス、衛星放送まで付いている。
食事がまた凄い。昼食が終わると看護士が1枚の紙を持ってくる。そこには夕食のメニューが書かれていて、メインは魚かビーフ、デザートはアイスかケーキなどすべて自分で選択できるのだ。すべてチェックを入れると夕食にはそれが出てくる。
「さすがアメリカン・ホスピタル、水までエビアンだ。」
それもそのはず、後で聞いた話だがこの病室は1泊10万円だったそうだ。

半年ぶりに見る母親は泣きそうな顔をしていたが、結構元気そうなボクをみて安心していた。日本ではもう死にかけと聞いていたので、もっとひどい状態だと思っていたらしい。
ボクは母親が来たのにも驚いたが、その荷物の多さにもっと驚いた。彼女はカバン一杯に即席麺、お茶づけ海苔、レトルトカレーにご飯などなどパリでコンビニでもするつもりなのかと思うほど買い込んでいた。
「だってトルコの大使館の人が、息子さん食欲なくて困っているみたいなので、行くならたくさん日本食持っていってあげてくださいっていってたから。。。」
翌日、とうとう骨髄検査の結果が出た。。。。。。。。。。To be continued
2005-09-16
海外旅行保険はほんとに必要?(part4)
月曜日の朝、いつもと変わらない病院の朝食を食べているとドクターがバタバタと入ってきた。
「なんで検査しないんだ!昨日検査するってうちの学生にいっただろ?」
ドクターは身振り手振り大きな声でそう言った。
「検査なんてもういい、今日は月曜日だ、早く日本大使館に連絡してくれ!ボクは自力でも日本に帰るからな!」
パンもひとかじりでやめたボクはそうドクターに言った。
実は今朝熱を計ると7度ちょっとに下がっていた。一週間ぶりに熱が下がっていたのだ。ボクはほんとに自力で日本に帰るつもりでいた。
それから30分もしないうちにドクターに呼ばれた。
「ヒデ電話だ、日本大使館だ!」
ドクターはあわててボクを呼びに来た。
「もしもし?私は日本大使館のTといいます。ドクターからあたなのことは聞きました。それで体調はいかがですか?」
その大使館の職員は丁寧な話し方だった。
「もう死にそうです。ボクはこんなところで死にたくありません。今日一週間ぶりに熱が下がりました、自力でも日本に帰るつもりです。」
「熱が下がったのですね、結構元気そうな声で安心しました。」
「今朝やっと熱が下がったのです。でも食欲がなく毎日ビスケットばかり食べています。もし今度熱が上がったらきっともうダメだと思います。このままここにいても食欲がないのでそっちで参ってしまう。とにかくこれが最後のチャンス、自力でも日本に帰りたいです。」
ボクは必死だった。熱は下がったがビスケットばかり食べていたので体力が落ちていくばかりだったからだ。
「でもそれはダメだとドクターが言っています。日本は遠すぎて必ず途中で血を吐いて死んでしまうと言っています。」
「わかっています。でもこのままここでじっとしてて死ぬより、熱が下がっている今がチャンスなんです!今度熱が上がったらもうダメです。。。。。」
「わかりました。とにかくご両親の連絡先を教えてください、私からご両親に連絡します。」
ボクは言われるままに実家の住所と電話番号を教えた。
その日の午後、父から病院に電話がかかってきた。
「おい!どうなんだ、大丈夫なのか?」
父の慌てぶりは普通じゃないのがすぐわかった。
「どうもこうも死にかけだよ、自力でも日本に帰りたいんだけど、ドクターが許可してくれない。」
「とにかくまだ生きてるんで安心した。保険会社にも連絡するからおとなしくしてるんだ、ドクターのいうこときいてな。」
帰国してから聞いた話だが、この時実家はパニック状態になっていたそうだ。それもそのはずだ。
「私トルコの日本大使館のTといいますが、お宅の息子さんトルコで死にかかっています。」
といきなり電話がかかってきたそうだ。
それから1時間もしないうちにまた電話がかかってきた。
「こんにちは、わたしM保険パリセンターのSといいます。ご両親から連絡をいただきお電話差し上げました。お身体の具合いはいかがですか?」
出発前に入っていた旅行保険の保険会社からである。久しぶりに聞く若い日本人女性の声にボクはちょっと元気がでた。
「ドクターにも言ったのですが、とにかくボクは日本に帰りたいんです、こんなところで死にたくないんです。」
ボクは同じことを繰り返したが、彼女の返事も同じものだった。
「それは日本は遠すぎるということでドクターが許可してくれません。」
「知っています、でも熱が下がった今しかチャンスがないんです!」
「とにかくドクターとご両親と日本大使館の方とで相談してみます。それまで待っていてください。」
彼女はそれだけ言って電話を切った。
次の日も熱は下がっていた。下がったと言っても7度ちょっとはあったが、食欲がないこと以外は体調はよかった。
「牛乳とオレオ」
3食いつもそれだけ。でもそのオレオも食べ飽きていた。
その日ボクは3通の遺書を書いた。会社の同僚と友人、それと旅に出る前に残してきた彼女。。。。。
水曜日の朝、いつものようにドクターは回診に来た。
「調子はどうだい?」
「Fine。。。。」
返事をするのも面倒くさい。
「ドクター、なんで日本に帰るの許可してくれないんだ、俺はもう熱が下がってるじゃないか!途中で死んでもあんたの責任じゃないし、とにかく自力で帰らせてくれ!」
「それはダメだよ。ここから日本までどれくらいかかる?」
「イスタンブールから10時間くらいかな。」
「じゃあきっと君はイスタンブールに着く前に死んでしまうよ。運良く生きていても飛行機の中で血を吐いて死ぬよ。」
それは自分でもわかっていた。でも何もしないでここにずっといるのがもう耐えられなかった。
その日の昼過ぎ、保険会社から電話がかかってきた。
「パリはどうですか?」
いつもの女性はいきなりそう言った。
「パリ?」
「そうパリです。そこの病院にいてもよくなるとは思えません。パリにはきちんとした設備の病院があります。そこで治療を受けてもらいます。さっきドクターとご両親、日本大使館の人と話したのですが、パリなら近いのでドクター付きという条件でドクターもOKをだしてくれました。」
「パリでもどこでもいいです!もうここは嫌です。食べ物も合わないし病気の前にそれでまいってしまいます!」
ボクは医局で大声を上げて叫んでいた。
「わかりました。では明日パリから医療チャータージェットをそちらへ飛ばします、折り返しその飛行機に乗ってパリまで飛んでください。」
「飛行機で迎えに来てもらえるのですか?」
パリまで自力で行くものと思っていたボクは驚いた。
「はい、パリからドクターを同乗させていきます。」
陸路専門のボクが、まさかパリまで飛行機で行けるとは夢にも思わなかった。
「わかりました!」
「それでそのフライト代は?。。。。。」とききそうになったがやめた。
これでオレオの食事ともお別れだ。何を喜んでいるかわからないドクターを横目にボクは走って病室に戻り荷造りをした。
翌木曜日、とうとうトルコから出発する日がきた。
「おいヒデ!飛行機がきたぞ、早く準備しろ!」
お昼前だっただろうか、ドクターに医局の人、それに採血の時に針を刺すのを失敗した看護婦、みんな病室にやってきた。
「元気でな、see you 」
「もう会いたくないよ。」
ボクはそう言って笑ってドクターと握手をした。。。。。。。。。。To be continued.
「なんで検査しないんだ!昨日検査するってうちの学生にいっただろ?」
ドクターは身振り手振り大きな声でそう言った。
「検査なんてもういい、今日は月曜日だ、早く日本大使館に連絡してくれ!ボクは自力でも日本に帰るからな!」
パンもひとかじりでやめたボクはそうドクターに言った。
実は今朝熱を計ると7度ちょっとに下がっていた。一週間ぶりに熱が下がっていたのだ。ボクはほんとに自力で日本に帰るつもりでいた。
それから30分もしないうちにドクターに呼ばれた。
「ヒデ電話だ、日本大使館だ!」
ドクターはあわててボクを呼びに来た。
「もしもし?私は日本大使館のTといいます。ドクターからあたなのことは聞きました。それで体調はいかがですか?」
その大使館の職員は丁寧な話し方だった。
「もう死にそうです。ボクはこんなところで死にたくありません。今日一週間ぶりに熱が下がりました、自力でも日本に帰るつもりです。」
「熱が下がったのですね、結構元気そうな声で安心しました。」
「今朝やっと熱が下がったのです。でも食欲がなく毎日ビスケットばかり食べています。もし今度熱が上がったらきっともうダメだと思います。このままここにいても食欲がないのでそっちで参ってしまう。とにかくこれが最後のチャンス、自力でも日本に帰りたいです。」
ボクは必死だった。熱は下がったがビスケットばかり食べていたので体力が落ちていくばかりだったからだ。
「でもそれはダメだとドクターが言っています。日本は遠すぎて必ず途中で血を吐いて死んでしまうと言っています。」
「わかっています。でもこのままここでじっとしてて死ぬより、熱が下がっている今がチャンスなんです!今度熱が上がったらもうダメです。。。。。」
「わかりました。とにかくご両親の連絡先を教えてください、私からご両親に連絡します。」
ボクは言われるままに実家の住所と電話番号を教えた。
その日の午後、父から病院に電話がかかってきた。
「おい!どうなんだ、大丈夫なのか?」
父の慌てぶりは普通じゃないのがすぐわかった。
「どうもこうも死にかけだよ、自力でも日本に帰りたいんだけど、ドクターが許可してくれない。」
「とにかくまだ生きてるんで安心した。保険会社にも連絡するからおとなしくしてるんだ、ドクターのいうこときいてな。」
帰国してから聞いた話だが、この時実家はパニック状態になっていたそうだ。それもそのはずだ。
「私トルコの日本大使館のTといいますが、お宅の息子さんトルコで死にかかっています。」
といきなり電話がかかってきたそうだ。
それから1時間もしないうちにまた電話がかかってきた。
「こんにちは、わたしM保険パリセンターのSといいます。ご両親から連絡をいただきお電話差し上げました。お身体の具合いはいかがですか?」
出発前に入っていた旅行保険の保険会社からである。久しぶりに聞く若い日本人女性の声にボクはちょっと元気がでた。
「ドクターにも言ったのですが、とにかくボクは日本に帰りたいんです、こんなところで死にたくないんです。」
ボクは同じことを繰り返したが、彼女の返事も同じものだった。
「それは日本は遠すぎるということでドクターが許可してくれません。」
「知っています、でも熱が下がった今しかチャンスがないんです!」
「とにかくドクターとご両親と日本大使館の方とで相談してみます。それまで待っていてください。」
彼女はそれだけ言って電話を切った。
次の日も熱は下がっていた。下がったと言っても7度ちょっとはあったが、食欲がないこと以外は体調はよかった。
「牛乳とオレオ」
3食いつもそれだけ。でもそのオレオも食べ飽きていた。
その日ボクは3通の遺書を書いた。会社の同僚と友人、それと旅に出る前に残してきた彼女。。。。。
水曜日の朝、いつものようにドクターは回診に来た。
「調子はどうだい?」
「Fine。。。。」
返事をするのも面倒くさい。
「ドクター、なんで日本に帰るの許可してくれないんだ、俺はもう熱が下がってるじゃないか!途中で死んでもあんたの責任じゃないし、とにかく自力で帰らせてくれ!」
「それはダメだよ。ここから日本までどれくらいかかる?」
「イスタンブールから10時間くらいかな。」
「じゃあきっと君はイスタンブールに着く前に死んでしまうよ。運良く生きていても飛行機の中で血を吐いて死ぬよ。」
それは自分でもわかっていた。でも何もしないでここにずっといるのがもう耐えられなかった。
その日の昼過ぎ、保険会社から電話がかかってきた。
「パリはどうですか?」
いつもの女性はいきなりそう言った。
「パリ?」
「そうパリです。そこの病院にいてもよくなるとは思えません。パリにはきちんとした設備の病院があります。そこで治療を受けてもらいます。さっきドクターとご両親、日本大使館の人と話したのですが、パリなら近いのでドクター付きという条件でドクターもOKをだしてくれました。」
「パリでもどこでもいいです!もうここは嫌です。食べ物も合わないし病気の前にそれでまいってしまいます!」
ボクは医局で大声を上げて叫んでいた。
「わかりました。では明日パリから医療チャータージェットをそちらへ飛ばします、折り返しその飛行機に乗ってパリまで飛んでください。」
「飛行機で迎えに来てもらえるのですか?」
パリまで自力で行くものと思っていたボクは驚いた。
「はい、パリからドクターを同乗させていきます。」
陸路専門のボクが、まさかパリまで飛行機で行けるとは夢にも思わなかった。
「わかりました!」
「それでそのフライト代は?。。。。。」とききそうになったがやめた。
これでオレオの食事ともお別れだ。何を喜んでいるかわからないドクターを横目にボクは走って病室に戻り荷造りをした。
翌木曜日、とうとうトルコから出発する日がきた。
「おいヒデ!飛行機がきたぞ、早く準備しろ!」
お昼前だっただろうか、ドクターに医局の人、それに採血の時に針を刺すのを失敗した看護婦、みんな病室にやってきた。
「元気でな、see you 」
「もう会いたくないよ。」
ボクはそう言って笑ってドクターと握手をした。。。。。。。。。。To be continued.
2005-09-11
海外旅行保険はほんとに必要?(part3)
「これは昨日採血した血液検査の結果です」
ドクターはそう言って一枚の白い紙を見せた。
「その結果、あなたの白血球と血小板の数値が異常に下がっています。何故こんな数値になったのかわかりませんが、このままでは明日死んでも不思議ではありません、leukopeniaだと思います」
ドクターは検査結果をみながらそう言った。
「leukopenia?」
医療用語の英語がわからないボクは辞書をひいてみたが載っていなかった。
「その単語は載っていない、何か他の言い方は?」
ドクターはボクの辞書を取り上げると単語を探し出した。
「leukemia」
ドクターはそこを指差した。
「白血病。。。。。」
leukemiaのところにはそう記してあった。
ボクはドクターにその血液検査の結果を見せてくれるように頼んだ。実は旅に出る前に血液検査の会社で働いていたので結果は見れば自分でわかる。
「ほんとだ。。。」
確かに検査結果は白血球と血小板の数値が異常に下がっている。特に血小板はもうなくなるんじゃないかというくらいの数値だった。
「なんでこんなことに、これじゃあほんとに明日死んでしまう。」
最初は風邪かなんかだと思っていたが、熱が下がらずマラリアだと思いこみ、大学病院に運ばれて白血病。この時やっと自分が大変なことになっていることに気づいた。
「ドクター、日本大使館に連絡して欲しい、ボクは日本に帰ります。こんなところで死ぬなら日本で死にたい。。。」
「今日は土曜日だ、大使館は休みだ」
ドクターは申し訳なさそうにそう言った。
「でも君の事を書いたFAXを大使館に送っておくよ。それで輸血をしようと思う。君の血液型は?」
そりゃそうだろう、とにかく輸血してもらわないと今夜にでも死にそうな状態だ。輸血しないと助からないくらいボクでもわかった。
しかしここ最近、輸血パックとかでエイズに感染する話が多く、ボクはとても心配だった。
「大丈夫、俺の血液型はO型だ、俺の血を輸血するよ」
ドクターはそういって腕をまくった。
「ドクターこそ病気持ってないだろうな、大丈夫か?」
「Trust me!」
ドクターは笑いながらそう言った。確かに訳のわからない輸血パックより安心かもしれない。
その日からボクは輸血とまだ下がらない熱の為に点滴をくりかえした。
白血球と血小板が減少しているといっても体調には変化はなかった。ただ熱があるだけで歩き回ることもできるし、何ら通常の時とかわらなかった。ただ病院の食事が毎日豆スープみたいなのとパンばかりで食欲はなかった。ボクは食事にはほとんど手を付けず、1Fの売店で売っているオレオのビスケットばかり食べていた。普段は高くて買わないオレオのビスケット、この時ばかりはためらうことなく買って食べた。

翌日曜日、ボクはまだ生きていた。
「気分はどうだい?」
午前の回診に来たドクターは昨日より明るい顔をしていた。
「熱はまだあるけど食欲がなくて身体がだるい、元気がでないよ。早く日本に帰りたい。」
ビスケットばかり食べているせいか、体力が日増しになくなっていくような気がした。
「それで提案なんだが、骨髄の検査をさせてくれないか?」
「骨髄検査?」
「そうだ。血小板は骨髄で作られている。骨髄を調べれば君の身体の中で血小板を作っているけどなくなっていっているのか、初めからつくっていないのかがわかるんだ。」
骨髄検査は知っていた。胸と腰の所に針を打って骨髄液を採取するのだ。大した検査ではないが針を刺すときに痛い。
大学病院といっても日本のどんな病院よりボロく、日増しに元気のなくなっているボクはそんなことはしたくなかった。
「検査は嫌です。早く日本に帰りたい、こんなところで死にたくない。。。」
ボクは何を言われても「日本に帰る」の一点張りだった。
その日の午後、ドクターが一人の男を連れてきた。何でもこの大学で唯一日本語が話せるそうだ。
ドクターは彼をおいて「しばらく話してな」と言って出ていった。
彼はベッドの横にあった椅子に座るといきなり話しだした。
「あなた何故検査しない?」
彼の日本語は上手くなく、ドクターの英語と同じで直訳だ。
「痛いから嫌なんだ」
設備がボロいなんて言えないボクはそう誤魔化した。
「あなた痛いのと死ぬのどっちいい?ボクは死ぬのは嫌だ、痛くても検査する。」
「。。。。。」
確かに死んでしまっては何もかも終わり。それくらいの判断もできないくらいボクは弱っていたみたいだった。
「するする、検査するよ。ボクも死にたくないよ。明日検査するってドクターに言っておいて。」
「わかった、今から言いに行ってくるよ」
彼は笑って出ていった。
その夕方、いつものように若い看護婦が採血にきた。この時彼女は2回ボクの腕に針を刺すのを失敗した。それが痛いというよりとても腹が立ったボクは彼女を怒鳴りつけた。普段ではこんなことでは怒らないが、いらいらしていたボクはまだ二十歳そこそこの彼女を怒鳴り散らした。
「I'm sorry。。。」
彼女は英語は話せないが、ボクが怒っているというのわかるらしく、か細い声でそう言った。
「I'm sorry? No sorry!」
ボクは更に怒鳴り散らした。
「もう明日の検査はしない!」
彼女は「検査しない」とボクが言ったのがわかったらしく、逆にトルコ語で「何で検査しない!」みたいなことを言って逆ギレしたように大きな声でボクを怒鳴ってきた。
「俺は明日自力でも日本に帰るからな!」
「You tomorrow die!」
そう彼女は捨てセリフを残して部屋を出ていった。
そして翌日、大使館が開く月曜日がやってきた。。。。。。。。To be continued
ドクターはそう言って一枚の白い紙を見せた。
「その結果、あなたの白血球と血小板の数値が異常に下がっています。何故こんな数値になったのかわかりませんが、このままでは明日死んでも不思議ではありません、leukopeniaだと思います」
ドクターは検査結果をみながらそう言った。
「leukopenia?」
医療用語の英語がわからないボクは辞書をひいてみたが載っていなかった。
「その単語は載っていない、何か他の言い方は?」
ドクターはボクの辞書を取り上げると単語を探し出した。
「leukemia」
ドクターはそこを指差した。
「白血病。。。。。」
leukemiaのところにはそう記してあった。
ボクはドクターにその血液検査の結果を見せてくれるように頼んだ。実は旅に出る前に血液検査の会社で働いていたので結果は見れば自分でわかる。
「ほんとだ。。。」
確かに検査結果は白血球と血小板の数値が異常に下がっている。特に血小板はもうなくなるんじゃないかというくらいの数値だった。
「なんでこんなことに、これじゃあほんとに明日死んでしまう。」
最初は風邪かなんかだと思っていたが、熱が下がらずマラリアだと思いこみ、大学病院に運ばれて白血病。この時やっと自分が大変なことになっていることに気づいた。
「ドクター、日本大使館に連絡して欲しい、ボクは日本に帰ります。こんなところで死ぬなら日本で死にたい。。。」
「今日は土曜日だ、大使館は休みだ」
ドクターは申し訳なさそうにそう言った。
「でも君の事を書いたFAXを大使館に送っておくよ。それで輸血をしようと思う。君の血液型は?」
そりゃそうだろう、とにかく輸血してもらわないと今夜にでも死にそうな状態だ。輸血しないと助からないくらいボクでもわかった。
しかしここ最近、輸血パックとかでエイズに感染する話が多く、ボクはとても心配だった。
「大丈夫、俺の血液型はO型だ、俺の血を輸血するよ」
ドクターはそういって腕をまくった。
「ドクターこそ病気持ってないだろうな、大丈夫か?」
「Trust me!」
ドクターは笑いながらそう言った。確かに訳のわからない輸血パックより安心かもしれない。
その日からボクは輸血とまだ下がらない熱の為に点滴をくりかえした。
白血球と血小板が減少しているといっても体調には変化はなかった。ただ熱があるだけで歩き回ることもできるし、何ら通常の時とかわらなかった。ただ病院の食事が毎日豆スープみたいなのとパンばかりで食欲はなかった。ボクは食事にはほとんど手を付けず、1Fの売店で売っているオレオのビスケットばかり食べていた。普段は高くて買わないオレオのビスケット、この時ばかりはためらうことなく買って食べた。

翌日曜日、ボクはまだ生きていた。
「気分はどうだい?」
午前の回診に来たドクターは昨日より明るい顔をしていた。
「熱はまだあるけど食欲がなくて身体がだるい、元気がでないよ。早く日本に帰りたい。」
ビスケットばかり食べているせいか、体力が日増しになくなっていくような気がした。
「それで提案なんだが、骨髄の検査をさせてくれないか?」
「骨髄検査?」
「そうだ。血小板は骨髄で作られている。骨髄を調べれば君の身体の中で血小板を作っているけどなくなっていっているのか、初めからつくっていないのかがわかるんだ。」
骨髄検査は知っていた。胸と腰の所に針を打って骨髄液を採取するのだ。大した検査ではないが針を刺すときに痛い。
大学病院といっても日本のどんな病院よりボロく、日増しに元気のなくなっているボクはそんなことはしたくなかった。
「検査は嫌です。早く日本に帰りたい、こんなところで死にたくない。。。」
ボクは何を言われても「日本に帰る」の一点張りだった。
その日の午後、ドクターが一人の男を連れてきた。何でもこの大学で唯一日本語が話せるそうだ。
ドクターは彼をおいて「しばらく話してな」と言って出ていった。
彼はベッドの横にあった椅子に座るといきなり話しだした。
「あなた何故検査しない?」
彼の日本語は上手くなく、ドクターの英語と同じで直訳だ。
「痛いから嫌なんだ」
設備がボロいなんて言えないボクはそう誤魔化した。
「あなた痛いのと死ぬのどっちいい?ボクは死ぬのは嫌だ、痛くても検査する。」
「。。。。。」
確かに死んでしまっては何もかも終わり。それくらいの判断もできないくらいボクは弱っていたみたいだった。
「するする、検査するよ。ボクも死にたくないよ。明日検査するってドクターに言っておいて。」
「わかった、今から言いに行ってくるよ」
彼は笑って出ていった。
その夕方、いつものように若い看護婦が採血にきた。この時彼女は2回ボクの腕に針を刺すのを失敗した。それが痛いというよりとても腹が立ったボクは彼女を怒鳴りつけた。普段ではこんなことでは怒らないが、いらいらしていたボクはまだ二十歳そこそこの彼女を怒鳴り散らした。
「I'm sorry。。。」
彼女は英語は話せないが、ボクが怒っているというのわかるらしく、か細い声でそう言った。
「I'm sorry? No sorry!」
ボクは更に怒鳴り散らした。
「もう明日の検査はしない!」
彼女は「検査しない」とボクが言ったのがわかったらしく、逆にトルコ語で「何で検査しない!」みたいなことを言って逆ギレしたように大きな声でボクを怒鳴ってきた。
「俺は明日自力でも日本に帰るからな!」
「You tomorrow die!」
そう彼女は捨てセリフを残して部屋を出ていった。
そして翌日、大使館が開く月曜日がやってきた。。。。。。。。To be continued
2005-09-05
海外旅行保険はほんとに必要?(part2)
4日目の朝も熱は38度を少し超えていた。
「これは普通の風邪じゃないな」
ボクはフロントでこの街で一番大きな病院はどこかと尋ねた。
レモンを持ってきてくれた青年は300mほど行ったところにあると教えてくれたが、心配なので一緒について来てくれるという。
ボクは熱が下がるまで入院するつもりだったので、ホテルをチェックアウトして荷物を担いで彼と一緒に病院へ向かった。
病院は2階建てだったが、街の広さから考えるとかなり大きめだ。レモンの彼は受付でなにやら話をして「あとは大丈夫」といって先に帰っていった。ボクは「世話になった」と握手を求めた。
看護婦はベッドが10ほど並ぶ部屋に案内すると、ここに寝るように手で合図した。もちろん英語は通じない。しばらくして若い女医さんが入ってきた。こんな田舎に留学生なんかいるわけないが、彼女の顔つきはあきらかにトルコ人ではない、それに英語もボクよりずっと堪能だった。
ボクは今まで熱がずっと下がらないこと。イスタンブールからのバスの中での症状。インドのデリーからトルコに入ったことなどを彼女に話し、間違いなくマラリアだと思うので検査をして欲しいと伝えた。
「ここでは検査はできません。ここから500mくらい行ったところに検査センターがあるのでそこへ行って検査を受けてください。電話で連絡しておきます。」
「500m....」
この日は朝からかなり暑く、熱がある身体で500mはかなりきつかった。それでもボクは荷物を持って言われるままに検査センターへ向かった。
検査は指先をカッターのようなもので指先を切り、出てきた血をプレパラートに塗りつけるものだった。看護婦は作業が終わると病院に帰って待っていてくださいという。それなら荷物を持ってこなくてよかったのにと、再び500mを病院に向かって歩きだした。このころはまた意識がもうろうとしてて倒れそうだったのを憶えている。
病院で1時間ほど寝ながら検査結果を待った。
「マラリアは陰性です。」
さっきの若い女医は簡単のそうボクに告げた。
「でも熱が下がらないのです。熱が下がるまでここに入院させてください。」
「それはダメです、ここには外国人は入院することができません。とりあえず点滴を打って様子をみましょう。」
冷たい感じではなかったが、彼女はボクにそう言うと看護婦になにやら話をして出て行った。
それからボクは半日ほど点滴を打ったが熱は一向に下がる気配がない。入院ができないなら夜になるとホテルに追い返されるのだろうか?そんなことを心配してるとさっきの女医さんが入ってきた。
「ここから2kmほどいったところに別の病院があります。そこに入院してください」
「2km...」
もうこれは歩ける距離じゃない。ここにおいてもらえないなら仕方ない。ボクは病院の前からタクシーに乗り込んだ。
その病院は「病院」というより「保養所」のようなところで、外来患者みたいな人は誰もいない。ここで出てきた女医さんはとびきり美人だった。ミニにノースリーブ、その上に白衣とかなり色っぽい。彼女はボクにさっさと診察台に寝転んでお尻をだすように指示した。
「お尻に注射しますからね」
言われるままにボクはお尻を出したが、その注射はどんなものだったかわからないが、しばらく歩けないほど強烈な痛みだった。
「あなたはここには入院できません。隣街のカイセリに大学病院があるからそこへ行って入院してください」
彼女はそういって何やらすらすら手紙を書き出した。
「これを向こうの病院に渡せばわかります。」
彼女はそう言ってボクに手紙を渡した。ボクは手紙より彼女の長い脚が気になっていた。
どれくらい走っただろうか。ボクはタクシーの中で眠ってしまって気づかなかったが、目が醒めるともうあたりは真っ暗だった。
病院に着いたのは夜8時ごろ、大学病院というだけあって高層ビル、日本の病院とかわならい概観だ。ボクは受付で例の手紙を渡した。
しばらくすると一人のドクターが下りてきた。30半ばくらいだろうか、トルコ人特有の浅黒い顔をしている。彼は手紙を読むと「ノープロブレム」といって横にあった台車に寝るようにボクに言った。
それからボクは検査室に運ばれて採血を済まし、そのまま10階くらいにある大部屋のベッドに寝かされた。
とても長く辛い一日だった。
翌朝土曜日の朝、それは今でも鮮明に憶えている。
昨日のドクターと看護婦、それに二人の若いドクターが一緒に入ってきた。
「How are you ?」
ドクターは英語があまり得意じゃないようで辞書を携帯している。
「まだ熱があります。検査でマラリアではないっていわれたのですが、ボクは絶対マラリアだと思います。」
ドクターはしばらくの間黙っていたが、その顔はかなり険しく、他のドクターの顔つきも普通じゃなかった。
「maybe you die ....」
ドクターは小さな声でそう言った。
「はぁ?」
ボクはそのドクターの言葉をよく理解できないでいた。
しばらく間をあけて再度ドクターがつぶやいた。
「meybe die...」
「maybe die?ボクが?」
「meybe.」
ドクターの英語は直訳で実にわかりやすかった。
「死ぬっていつ!(ふざけやがって!)」
ボクはかなり興奮していて、他の患者がみんな見てるのもかまわず叫んだ。
「meybe tomorrow....」
「tomorrow?(いい加減なこと言いやがって!) Why !」
怒鳴り散らすボクにドクターは一枚の紙をボクに見せた.....To be continued
「これは普通の風邪じゃないな」
ボクはフロントでこの街で一番大きな病院はどこかと尋ねた。
レモンを持ってきてくれた青年は300mほど行ったところにあると教えてくれたが、心配なので一緒について来てくれるという。
ボクは熱が下がるまで入院するつもりだったので、ホテルをチェックアウトして荷物を担いで彼と一緒に病院へ向かった。
病院は2階建てだったが、街の広さから考えるとかなり大きめだ。レモンの彼は受付でなにやら話をして「あとは大丈夫」といって先に帰っていった。ボクは「世話になった」と握手を求めた。
看護婦はベッドが10ほど並ぶ部屋に案内すると、ここに寝るように手で合図した。もちろん英語は通じない。しばらくして若い女医さんが入ってきた。こんな田舎に留学生なんかいるわけないが、彼女の顔つきはあきらかにトルコ人ではない、それに英語もボクよりずっと堪能だった。
ボクは今まで熱がずっと下がらないこと。イスタンブールからのバスの中での症状。インドのデリーからトルコに入ったことなどを彼女に話し、間違いなくマラリアだと思うので検査をして欲しいと伝えた。
「ここでは検査はできません。ここから500mくらい行ったところに検査センターがあるのでそこへ行って検査を受けてください。電話で連絡しておきます。」
「500m....」
この日は朝からかなり暑く、熱がある身体で500mはかなりきつかった。それでもボクは荷物を持って言われるままに検査センターへ向かった。
検査は指先をカッターのようなもので指先を切り、出てきた血をプレパラートに塗りつけるものだった。看護婦は作業が終わると病院に帰って待っていてくださいという。それなら荷物を持ってこなくてよかったのにと、再び500mを病院に向かって歩きだした。このころはまた意識がもうろうとしてて倒れそうだったのを憶えている。
病院で1時間ほど寝ながら検査結果を待った。
「マラリアは陰性です。」
さっきの若い女医は簡単のそうボクに告げた。
「でも熱が下がらないのです。熱が下がるまでここに入院させてください。」
「それはダメです、ここには外国人は入院することができません。とりあえず点滴を打って様子をみましょう。」
冷たい感じではなかったが、彼女はボクにそう言うと看護婦になにやら話をして出て行った。
それからボクは半日ほど点滴を打ったが熱は一向に下がる気配がない。入院ができないなら夜になるとホテルに追い返されるのだろうか?そんなことを心配してるとさっきの女医さんが入ってきた。
「ここから2kmほどいったところに別の病院があります。そこに入院してください」
「2km...」
もうこれは歩ける距離じゃない。ここにおいてもらえないなら仕方ない。ボクは病院の前からタクシーに乗り込んだ。
その病院は「病院」というより「保養所」のようなところで、外来患者みたいな人は誰もいない。ここで出てきた女医さんはとびきり美人だった。ミニにノースリーブ、その上に白衣とかなり色っぽい。彼女はボクにさっさと診察台に寝転んでお尻をだすように指示した。
「お尻に注射しますからね」
言われるままにボクはお尻を出したが、その注射はどんなものだったかわからないが、しばらく歩けないほど強烈な痛みだった。
「あなたはここには入院できません。隣街のカイセリに大学病院があるからそこへ行って入院してください」
彼女はそういって何やらすらすら手紙を書き出した。
「これを向こうの病院に渡せばわかります。」
彼女はそう言ってボクに手紙を渡した。ボクは手紙より彼女の長い脚が気になっていた。
どれくらい走っただろうか。ボクはタクシーの中で眠ってしまって気づかなかったが、目が醒めるともうあたりは真っ暗だった。
病院に着いたのは夜8時ごろ、大学病院というだけあって高層ビル、日本の病院とかわならい概観だ。ボクは受付で例の手紙を渡した。
しばらくすると一人のドクターが下りてきた。30半ばくらいだろうか、トルコ人特有の浅黒い顔をしている。彼は手紙を読むと「ノープロブレム」といって横にあった台車に寝るようにボクに言った。
それからボクは検査室に運ばれて採血を済まし、そのまま10階くらいにある大部屋のベッドに寝かされた。
とても長く辛い一日だった。
翌朝土曜日の朝、それは今でも鮮明に憶えている。
昨日のドクターと看護婦、それに二人の若いドクターが一緒に入ってきた。
「How are you ?」
ドクターは英語があまり得意じゃないようで辞書を携帯している。
「まだ熱があります。検査でマラリアではないっていわれたのですが、ボクは絶対マラリアだと思います。」
ドクターはしばらくの間黙っていたが、その顔はかなり険しく、他のドクターの顔つきも普通じゃなかった。
「maybe you die ....」
ドクターは小さな声でそう言った。
「はぁ?」
ボクはそのドクターの言葉をよく理解できないでいた。
しばらく間をあけて再度ドクターがつぶやいた。
「meybe die...」
「maybe die?ボクが?」
「meybe.」
ドクターの英語は直訳で実にわかりやすかった。
「死ぬっていつ!(ふざけやがって!)」
ボクはかなり興奮していて、他の患者がみんな見てるのもかまわず叫んだ。
「meybe tomorrow....」
「tomorrow?(いい加減なこと言いやがって!) Why !」
怒鳴り散らすボクにドクターは一枚の紙をボクに見せた.....To be continued
 shusa
shusa Link
Link 0
0 スナフの旅
スナフの旅 10:17
10:17